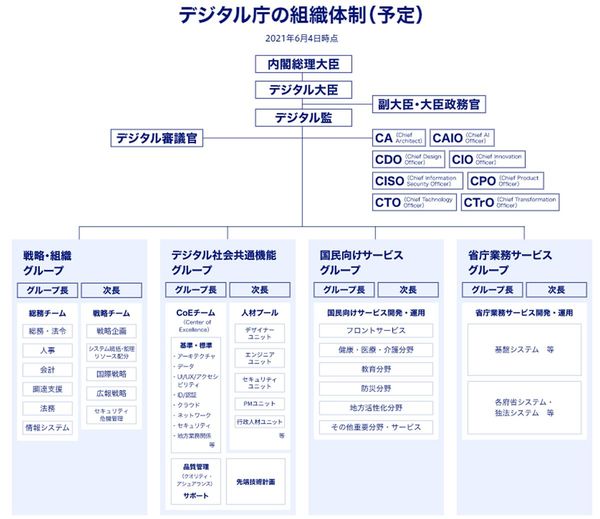新潮社フォーサイトに7月2日に掲載された拙稿です。ぜひご一読ください。オリジナルページ→
https://www.fsight.jp/articles/-/48062
6月に閉幕した通常国会で、国家公務員の定年を65歳に引き上げる国家公務員法などの改正法が可決成立した。国会審議では、新型コロナウイルスの感染再拡大や東京オリンピック・パラリンピックの扱いにもっぱら関心が向き、公務員の定年延長に関する議論はほとんど注目されなかった。というのも、自民・公明の与党だけでなく、立憲民主党などの野党も公務員の定年延長には賛成で、まったく争点にならなかったというのが正しい。
現在60歳の定年を2023年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げ、2031年度に65歳にする。民間企業で多く採用されている「再雇用」ではなく、定年が延長される。現在も希望者は65歳まで再雇用する「再任用制度」が存在するが、にもかかわらず「定年」を延長したのは、これで身分保障と待遇がよりよくなるからだ。
連合の「悲願」により立民も「賛成」
民間では60歳で再雇用された場合、大幅に給与が下がるのが普通だ。ところが、今回の法律改正では60歳以前の7割を当面保証している。民間企業で働く人々は、新型コロナの影響で、企業業績が悪化していることから、廃業・倒産の危機に直面したり、失業のリスクに晒されている。失業しないまでも、残業代がなくなり収入が大幅に減っている人も少なくない。もともと公務員は失業のリスクがゼロで、給与も景気変動に関係なく増え続ける。そんな十分に保証されている公務員を、民間での定年延長の流れよりも先に引き上げる理由があったのか。「経済の立て直しに先んじて公務員の定年延長を急ぐ必要があったのか疑問が残る。(中略)一足飛びに、定年延長も、60歳以降の給与保証も実施することについて、国民の理解を得るための審議を尽くしたとは言えない」(北海道新聞社説)という指摘が出るのは当然だろう。
しかも、60歳以上はそれ以前の7割という給与水準も、いつまで守られるか分からない。人事院などの資料によると「60歳を超える職員の俸給月額は60歳前の70%の額とし、俸給月額の水準と関係する諸手当等は60歳前の7割を基本に手当額等を設定(扶養手当等の手当額は60歳前と同額)」するとしているものの、7割というのは「当分の間」の措置だという。ほとぼりが覚めれば、7割からさらに引き上げることもありそうだ。
60歳に達した段階で降格する「役職定年制」も導入することが決まった。役所のポストは定数が決まっているため、高齢職員が居座ればポストが空かないからだ。だが、これにも例外があるようで、高齢職員がポストにとどまり続ける可能性がある。
国民からみればまさに「役人天国」だが、霞が関も永田町も、これで世の中が納得する「世間相場」だと思っているのだろうか。
「菅さんは役所の嫌がることはやらない人」
実はこの法案、昨年も閣議決定され通常国会に提出されていた。ところが公務員全体の定年延長と一体で出された検察庁法改正に焦点が当たり、国民の強い反発を食って頓挫したのだ。安倍晋三内閣に近いとされた黒川弘務・東京高検検事長の定年を法解釈の変更で延長した恣意的な人事を、糊塗するための法改正ではないかといった批判が噴出し、ツイッターで数百万件の抗議の投稿がなされるなど、まさに「炎上」状態となった。結局、安倍内閣は検察庁法改正を断念、一体だった公務員全体の定年引き上げも見送った。
ちなみに、野党は検察庁法の改正については猛烈に批判していたものの、法案成立断念の話が出ると、公務員法の改正だけでも通し、定年引き上げを行うべきだと自民党にかけあった。というのも、立憲民主党の支持母体である連合は公務員などの組合組織の支援を受けており、定年引き上げはむしろ悲願だったからだ。さすがにどさくさ紛れに定年延長を決めれば国民の怒りを買うとみた安倍首相らが法案成立断念を決めたとされる。
「菅さんは役所の縦割り打破など、一見役所に厳しいことを言っているように見えますが、実際は役所の嫌がることはやらない人です。役所にそっぽを向かれれば政権基盤が揺らぐと思っているのです」と自民党のベテラン議員は言う。新型コロナで経済が回復せず、民間の雇用や給与にまだまだ不安がある中で、公務員だけ優遇する定年延長法案を国会に出す決断をしたのは菅首相自身だったという。
まさに、与野党に支えられた「役人優遇」だが、当の霞が関の官僚の中には浮かない顔をしている中堅幹部が少なからずいる。
後続世代は50代半ばまで「雑巾がけ」に
「定年延長で間違いなく主要ポストの高齢化が進みます。今でも課長になるまでに20年間以上雑巾がけが必要とされていますが、これからは定年延長が進めば、50代半ば過ぎないとまともな権限を持てないかもしれません」(経産省の中堅幹部)
優秀な人材が霞が関に来なくなったと言われて久しい。仕事が忙しく休めない「ブラックな職場」が忌避されている、「給与が安いから外資に流れてしまう」「天下りが減り生涯年収が読めなくなった」といったことがベテラン官僚の口から漏れる。だが、若手に聞くと外資に行くのは、報酬が高いことばかりが理由ではなく、「若いうちに大きな仕事を任せてくれるので経験を積める」(大学3年生)という理由を挙げる。実際、人気の外資コンサルティング・ファームに入った場合、働き方はモーレツで寝る時間もないほどだ。つまり、役人にならないのは、完全な入省年次主義で、年功序列のため、何年も下積みをさせられるということを嫌っている優秀な人材が多い。だとすると、今回の定年の延長は決定的にこうした優秀な人材をますます遠ざける結果になるだろう。
「今こそ、抜本的な公務員制度改革をやらないと霞が関はもちません」と財務省の幹部は言う。「今は年次主義の中で、上を見て忖度する人ばかりが偉くなるような仕組みです。民間の360度評価ではありませんが、多面的な評価で、年次を崩した人事を行えるようにしなければ、優秀な人ほど辞めてしまいます」
人材流出で霞が関の「神話」崩壊が止まらない
実際、経済産業省など主要官庁では、中堅の人材が次々に辞めていく現象が起きている。
最近、国会に提出した法案に誤字脱字や条文の誤りなどが見つかるケースが頻発している。「昔では考えられなかった事故。読み合わせする時間がなかったなどと言い訳していますが、実際には能力が圧倒的に欠如している人が増えました」と霞が関OBは嘆く。経産省が所管する「家賃支援給付金」550万円をだまし取った疑いで2人の経産キャリア官僚が逮捕されたが、「こんな意識の低い人間がキャリアに紛れ込んで来るようになるとは」と絶句する。
日本は政治家は三流だが、優秀な官僚機構に支えられているから問題ない、と戦後長い間言われ続けたが、いまやそれも「神話」となった。「公務員制度改革」に霞が関官僚が徹底抗戦してきたのも、優秀な官僚機構にダメな政治家が手を入れることへの抵抗感だった。しかし、今では有能な幹部官僚の間からもむしろ公務員制度改革を進めて、若くても有能な人材を抜擢するべきだという声が出始めている。年次ではなく実績によって多面的な人事評価を行う仕組みを作れば、官邸の権限を握った政治家が好き嫌いで人事を行うことも難しくなる。
国民の多くが気づかぬ間にこっそり通した公務員の定年延長が、ますます国民の政府に対する信用を損ない、霞が関の官僚に就こうという若者を減らしていくことになるだろう。