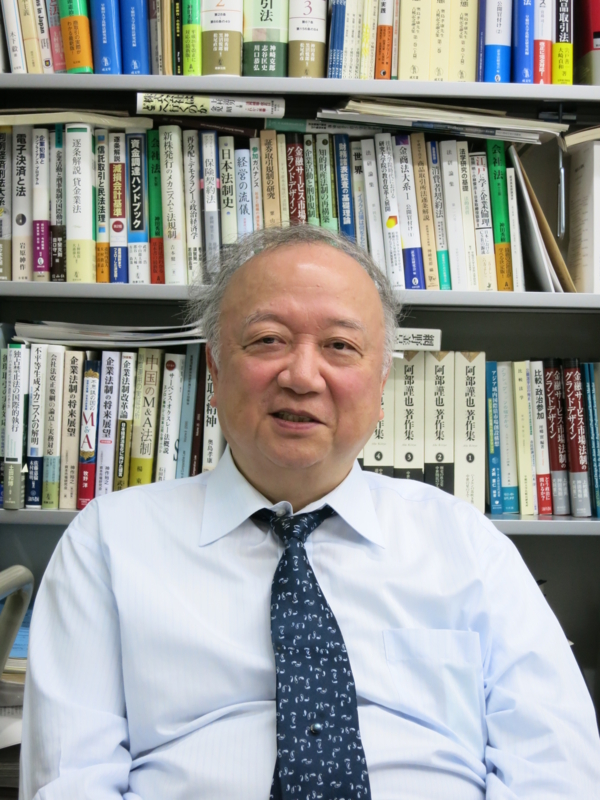地域おこしが成功するかどうか。ひとつの条件は「首長が本気なこと」です。真っ先に国家戦略特区に指定された兵庫県養父市の広瀬栄市長は腹のすわった根っからの改革派です。日経BPの「新・公民連携最前線」にアップされたインタビューを是非お読みください。オリジナルページ→ http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/433746/090800008/
安倍晋三内閣が規制改革の目玉と位置付ける「国家戦略特区」。その第1弾として2014年に指定された兵庫県養父(やぶ)市は、中山間地農業のモデルを目指す。その旗振り役である広瀬市長は、これまでも構造改革特区などで公民連携をフル活用してきた根っからの改革派だ。国家戦略特区に指定されて1年余り。現状と今後の展望について聞いた。(聞き手は磯山友幸)
――なぜ、国家戦略特区に手を挙げたのでしょうか。
これまでの特区と違い、首相のトップダウンで規制改革を進めるということなので、期待感はあります。とかく養父市が注目されているので、市民の間でも何かが起きそうだというムードが盛り上がってきました。
昨年度で一応の仕組みづくりが終わり、いよいよ規制改革を使った事業が動き出しています。特区内で認められた農業生産法人の設立要件の緩和を使って、すでに4社が法人を設立しました。市外の事業者が入ってきたことで、地域の農業者が変わっていく引き金になりました。
他人が儲けだすと、「何で俺にも声をかけなかったのか」という声が挙がるものですが、そんな声が市民の間から出て来る日も近いと期待しています。
――養父市の特区では、農地の売買や転貸に関する権限を、全国で初めて農業委員会から市長に移しました。
デメリットはほとんどないのです。代々受け継いできた農地を売る人の精神的な負担は非常に大きい。その許可を地域の代表である農業委員会に求めるのは嫌なものです。権限が市長に移ったことで、淡々と事務処理がされます。農業委員会の時には許可が下りるまで平均で26〜27日かかっていましたが、平均10日に縮まりました。これは週末をはさんでいるからで、月曜に出せば金曜に許可が出るというのが実態です。
――具体的に農地の流動化に役立っているのでしょうか。
去年10月から約半年で27件、約5ヘクタールの許可を出しました。あくまで目的は農業の振興です。その点を農業委員会も理解してくれました。農地移動の際に必要だった最低耕作面積は、従来は一部地域を除いて30アールでしたが、これを10アールに引き下げました。農業への参入を容易にするためです。
私の夢としては、これを1アールにまで引き下げたい。100平方メートル、30坪です。家庭菜園でも農家になれる。都市住民の中には専業で農家をやるのは嫌だが、家庭菜園ぐらいなら農作業をしたいという人がたくさんいます。農業の復活には、多様な担い手を創ることが不可欠です。周囲の農地を買い増して大規模化を目指してもよいし、集落全体で共同作業する集落営農でもよい。農業を産業として行う企業的な発想を持ち込んでもらってもよい。従業員として農業に携わるという担い手の形でもいい。そうした多様な担い手を創るためにも、農地がスムーズに取得できることがカギだったのです。
JAも新しいあり方を模索
――市長は常日頃、自主自立が大事だとおっしゃっています。
国家戦略特区でも養父市に必要な事だけをやらせて欲しいと言っています。自主自立と偉そうに言っても、財政力は弱い。自前の財源は25%です。国に養ってもらっている。山ばかりで人がまばらに住んでいる中山間地で、財政を自立させるのは難しい。それでも25%を35、40と引き上げる努力をすることが大事なのです。農業を収入のある産業に転換していくことが養父にとって不可欠なわけです。特区で新しい風が吹いて、こんな農業があったのだ、と市民の皆が気づくことが大切です。
――オリックスが養父での農業に乗り出していますね。
特区になる前から、廃校になった小学校の体育館を活用した野菜工場などを始めていました。特区内では、「やぶファーム株式会社」という農業生産法人が生まれましたが、ここにはオリックスと、市の100%出資会社である「やぶパートナーズ株式会社」、地元農家に加えて「JAたじま」が参画しました。ご承知のとおり、オリックスの宮内義彦・シニアチェアマンはJA改革の旗頭のような方です。そのオリックスと地元の農協であるJAたじまが一緒になって新しい形の農業を模索している。これは特区として象徴的な事だろうと思います。
――よくJAたじまが乗ってきましたね。
この際だから、新しいJAのあり方を模索してみるか、となったのではないでしょうか。JAも農家からだいぶ離れていた部分があるので、少し変わるべきだと思っておられたようです。組合長も改革派になりました。やぶファームに加わる事については、中央会との間で相当やり取りがあったようですが。
――特区の現場におられて、規制改革でまだまだ不十分と感じられる点はあるのでしょうか。
農業生産法人は、役員要件は緩和され、農業従事者が1人いれば設立できるようになりました。ところが出資規制が残っています。農業者が過半を出資しなければいけないのです。産業化に必要な大きな資本を企業に出してもらおうとすると、それを上回るおカネを農家が出さなければならない。そんな農家は、そうそういません。つまり、企業が出資したくてもできないのです。これでは仏作って魂入れずです。
企業が過半の資本を握ると、経営が苦しくなった時に、持っている農地を売却されかねないというのが反対の理由ですが、企業が保有する農地を、農地以外に使えないように規制すればよいのです。養父市では、市独自の農地の適正管理に向けた条例づくりを検討しています。もちろん全国初の取り組みですが。
養父市でできれば、どこでもできるはず
――市長は、これまでも構造改革特区を活用するなど、様々な取り組みを行って来ました。
私は合併前の八鹿町の職員出身ですが、ずっと、このままでは八鹿町はもたないと感じていました。民間企業からすれば公務員は安定していると思われますが、その源である町自体が崩壊してしまうと危機感を持ったのです。それで国が作ったPFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)の仕組みを真っ先に使って、温浴施設をPFIに変えたほか、道の駅も建設しました。また、構造改革特区では「どぶろく特区」なども実現した。失敗しても失うものはない、と考えたのです。
――2002年にオープンした「とがやま温泉天女の湯」は、日本のPFI事業としてはかなり早い時期に整備した事例ですね。
もともとは、ふるさと創生の1億円のうち6000万円を使って建設したものでした。町の職員として、その再生に取り組んだのですが、第3セクター方式しかないかな、と思い設立したものの、マネジメントのコストがかかりすぎて、500円の入浴料では到底もとが取れず、1年で解散しました。2000年ごろです。当時、政府がPFI法を作ったばかりで、これで行こうと考えたのです。BTO方式でまとめて、何とか実現しました。
――国家戦略特区に指定されて1年あまりが立ちましたが、振り返ってどうでしょうか。
所管省庁の抵抗の強さ、壁の厚さと高さを実感しています。首相がやれと言っているのに、各省庁はなかなか動かない。何もしなければ、日本の農業は荒廃する一方だということが分かっているのに、なかなか動こうとしません。そうは言っても、一歩一歩進めるしかありません。
今後も特区の枠組みを使って、養父市に必要な改革を進めていきたいと思います。中山間地の養父市で、儲かる農業を実現することができたならば、日本全国どこでも農業を再生できるのではないか。日本の農業再生は養父市から。そう信じて改革を進めていきたいと思います。
広瀬栄(ひろせ・さかえ)氏
1947年兵庫県八鹿町(現・養父市)生まれ。県立八鹿高を経て、71年、鳥取大学農学部卒業、建設会社に勤務。76年八鹿町役場に入る。産業課課長補佐、商工労政課長、企画商工課長、建設課長などを経て、2004年、養父市都市整備部長。05年助役兼都市整備部長、07年副市長に就任。08年10月に養父市長選挙に立候補し初当選。12年無投票再選。現在2期目。趣味は読書、ウォーキング、釣り。