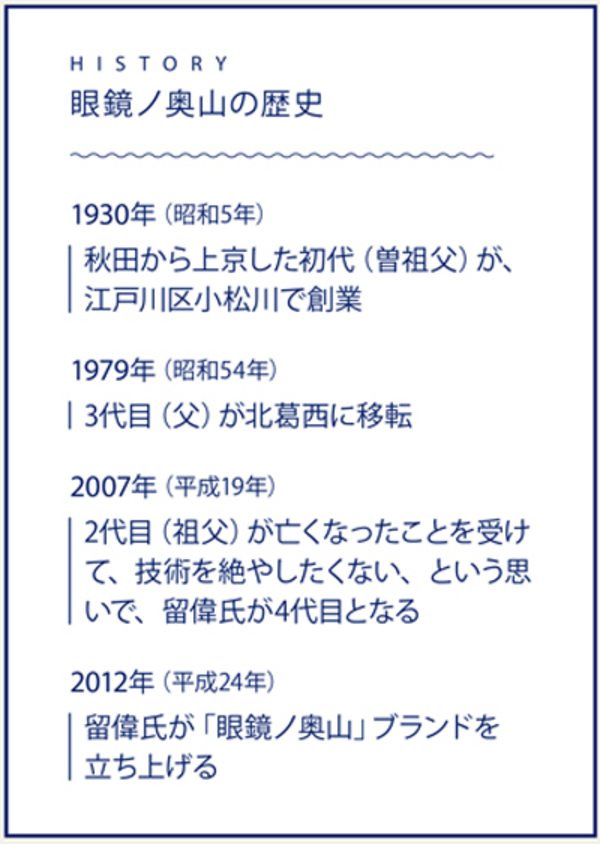現代ビジネスに12月10日に掲載された拙稿です。ぜひご一読ください。オリジナルページ→
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/90232
いまひとつ見えない
岸田文雄首相は12月6日の臨時国会冒頭、所信表明演説を行った。菅義偉前首相に比べ言語は明瞭で、キャッチフレーズも数多いが、なぜか、その中身が国民の心に刺さって来ない。巧言令色と言うべきか、言葉は巧みなのだが、具体的に何をやろうとしているのか、それでキャッチフレーズ通りの成果が上がるのか、いまひとつ見えない。首相自身の「信念」が乏しいのではないかと疑ってしまう。
そのキャッチフレーズの最たるものが「新しい資本主義」だろう。新型コロナ対策を強調するのは当然として、そのコロナが去った後、どんな日本を目指すのかという流れの中で、「新型コロナによる危機を乗り越えた先に私が目指すのは、『新しい資本主義』の実現です」と大見得を切った。
では、いったい新しい資本主義とは何なのか。
「人類が生み出した資本主義は、効率性や、起業家精神、活力を生み、長きにわたり、世界経済の繁栄をもたらしてきました。しかし、1980年代以降、世界の主流となった、市場や競争に任せれば、全てがうまくいく、という新自由主義的な考えは、世界経済の成長の原動力となった反面、多くの弊害も生みました」
総裁選以来、「新自由主義的政策は取らない」と繰り返し述べてきた岸田首相は、よほど新自由主義が嫌いとみえる。
「市場に依存し過ぎたことで、格差や貧困が拡大し、また、自然に負荷をかけ過ぎたことで、気候変動問題が深刻化しました。これ以上問題を放置することはできない」
批判の矛先は日本?
確かに、英国のサッチャー首相や米国のレーガン大統領が始めた市場原理を尊重する政策は「新自由主義」と言われ、停滞していた両国の経済を大きく復活させた一方で、格差拡大や環境問題などを引き起こしたのは事実だろう。そんな英国や米国で「新たな資本主義モデル」を模索する声が出るのはある意味当然と言える。岸田首相が「新自由主義」を採った英国や米国を批判するのなら分かる。
ところが、批判の矛先は日本自身だ。だが、本当に、日本が進めてきた小泉純一郎政権以降の政策はアベノミックスも含めて「新自由主義」で、その弊害が生まれるほどに推し進めてきたのか? だとしたら、なぜ、日本は米国や英国のように大きく経済成長せず、給与も増えず、企業も金融機関も世界競争に勝てずにジリ貧になっているのか。
そもそも、日本が現在抱える問題は、新自由主義的政策をとった結果だ、という前提自体が間違っているのではないか。
1990年代以降、中国もロシアも社会主義的政策を捨て、グローバル化の中で経済成長を目指してきた中で、日本だけがその流れに乗り遅れたのではないか。既得権を持つ伝統的な産業や企業を守ることを優先し、少子高齢化で将来無理が来ることが分かっていながら、社会主義的な政策を取り続けた。いわゆる「ショーワ」な日本と決別できなかった30年が今の問題を引き起こしているのではないか。
しかも、ここへきて「新自由主義的な政策は取らない」と言い、構造改革や規制緩和を封印することで、どんな「新しい」経済を作ろうというのか。「我が国としても、成長も、分配も実現する『新しい資本主義』を具体化します」というが、アベノミクスでもなかなか成果が上がらなかった成長を実現するのは容易なことではない。
まともな資本主義すら忌避している
「日本ならできる、いや、日本だからできる」。どこからそんな強い自信が生まれてくるのか。では、具体的に何が日本ならできる「新しい資本主義」なのか。
岸田首相は続ける。「我々には、協働・絆を重んじる伝統や文化、三方良しの精神などを、古来より育んできた歴史があります。だからこそ、人がしっかりと評価され、報われる、人に温かい資本主義を作れるのです」。
もちろん、自分だけ良ければいいというのではなく、社会全体に貢献する、弱者を助けていくというのは日本人の美徳である。だがそれは、皆が切磋琢磨した上で、成功する者が生まれ、その成功者が弱者を助けてきたというのが日本の歴史だろう。皆が我慢して等しく貧乏になればそれでいい、という話ではない。三方良しとは皆が豊かになることを言っているのであって、競争して成長していくことが前提だ。決して三方一両損ではない。
これまでも構造改革を否定する識者は「日本型経営」や「日本型のシステム」の良さを主張してきた。株式持ち合いが日本経済の根幹だとか、ワンマン社長を許容する日本型のコーポレート・ガバナンスも良い点が多いなどと言ってきたのは、ひとえに「グローバル化」で世界が改革を進めることに反対していたに過ぎない。つまり、「日本型経営」というものを突き詰めた上で、磨きをかけてきたわけではないのだ。
「三方良し」にしても、日本経済の仕組みにどう落とし込んでいくのかという正面からの議論はほとんど行われて来なかった。ただ、欧米型のガバナンスは嫌だ、競争が激しくなる新規参入を認める規制緩和は嫌だ、と言ってきただけだ。
「皆さん。明治維新、戦後高度成長、日本は幾多の奇跡を実現してきました」と岸田首相は力を込めた。だが、明治期の企業家も、戦後の企業家も、世界との競争に勝ち、豊かさを実現してきた。まともな資本主義すら忌避して、「新しい資本主義」など生み出せるはずもない。
まずしっかり「稼げ」よ
具体策として打ち出した、成長戦略も新味があるものはほとんどない。イノベーションもアベノミクスの時代から言い続けてきた。デジタル化も国に言われるまでもなく民間はどんどん進めている。
そもそも「10兆円の大学ファンド」は、岸田首相が嫌いな「市場」の力を借りて運用益を上げ、それを原資に研究費を助成しようというものだ。これは新自由主義的な仕組みではないのだろうか。
デジタル田園都市国家構想にしても、これまでの地域創生とどこが違うのか。もちろん、政策を進める役人の顔ぶれは変わらないので、看板だけ変えて同じことをやるほかないのだろう。
円安政策を続けた結果、国際的な購買力が低下し、どんどん貧しくなっていく日本。これをどう立て直していくのか。「新しい」などと言わず、もっとしっかり「資本主義」をやって、まずは稼ぐこと。その上で、分配や、弱者救済のセーフティーネット整備に力を入れるべきだろう。
![Wedge (ウェッジ) 2021年 6月号 [雑誌] Wedge (ウェッジ) 2021年 6月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51tQFkx7QkS._SL500_.jpg)