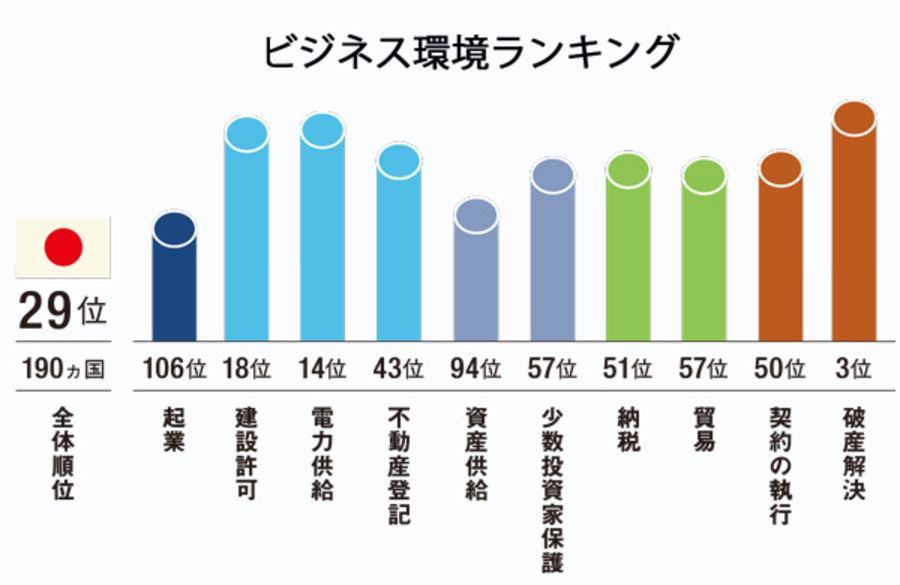ITmediaビジネスオンラインに連載中の『滅びる企業 生き残る企業』に6月23日に掲載されました。是非ご一読ください。オリジナルページ→
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2006/23/news020.html
巨額の赤字に陥った日産自動車は再起できるのか。
5月28日に発表した2020年3月期決算は、最終損益が6712億円の赤字になった。最終赤字はリーマンショック後の2009年3月期(2337億円の赤字)以来。赤字額としてはカルロス・ゴーン元会長が着任して改革に乗り出した2000年3月期の6843億円に次ぐ規模となった。
20年前の決算では、日本の製造業としては過去最大の赤字を出す一方で、日産が保有していた持ち合い株式や工場跡地など資産を一気に売り払い、翌年度からV字回復を遂げた。ゴーン・マジックとも呼ばれたが、会計学者などからは「ビッグバスだ」と言った批判も出た。ビッグバスとは文字通り「大きな風呂」の意味で、過去の負の遺産を一気に洗い流すことで、翌期以降の回復を演出する手法で、巨額赤字は実態以上の過度なものだったと指摘された。
「販売台数激減」の理由は固有の事情
では、今回も同様に、巨額の損失は「ビッグバス」なのだろうか。
決算発表で日産は、販売活動の悪化が2291億円の利益減少要因となったとした。実際に全世界での販売台数は10.6%減と大きく落ち込んだ。新型コロナウイルスの蔓延(まんえん)で1月から3月にかけて世界の自動車需要が大きく落ち込んだが、日産の台数減少は新型コロナが主因ではない。中国での販売台数は1.1%減になっているが、これは19年12月までの数字が連結対象になっており、新型コロナの影響が出た2月3月の数字は入っていない。日本での販売台数も10.3%減になったが、新型コロナの影響が大きくなったのは4月以降。つまり、日産固有の問題として販売台数が激減しているという面が強い。
そうした本業の悪化に加えて、最終赤字の多くは、「減損」によるものだと説明している。事業用資産の減損4634億円と固定資産の減損586億円の合計5220億円が赤字の主因だとした。
固定資産の帳簿価格を引き下げる「減損」を行えば、翌期以降の減価償却費が軽くなる。もっともこれは事業を継続していた場合の話で、例えば工場閉鎖などに伴う減損ならば、将来は利益が上がらず、V字回復はおぼつかない。
普通の会社ならば、これだけ巨額の損失を出せば、手元資金が枯渇し、倒産しかねない。だが、内田誠社長兼CEO(最高経営責任者)は「現時点では十分な資金が確保できている」と述べ、資金繰りに不安はないことを強調した。もちろん、減損は基本的にキャッシュ・アウトしない、つまり資金が流出しないので手元資金には影響しない。自動車事業の手元資金だけでも期末に1兆4946億円に達し、さらに4月から5月にかけて7126億円の資金を調達したことを示し、「十分」だとしたのだ。さらに金融機関との間で結んでいるコミットメントライン(融資枠)もまだ1兆3000億円が未使用だとした。
問題は、今後、どれぐらい自動車事業など本業でキャッシュを稼げるかにかかっているが、2020年3月期は営業キャッシュフローが2124億円の赤字(流出)、設備投資などの投資キャッシュフローが4518億円の赤字(流出)で、いわゆるフリーキャッシュフロー(FCC)は6410億円の赤字(流出)になっている。これが販売悪化でさらに拡大していけば、資金繰りは一気に厳しさを増す。ゴーン改革の時と違い、売却できる土地や有価証券はほとんどない。今回の巨額赤字は、ゴーン改革時の余裕がある「ビッグバス」とはだいぶ様相を異にしているのだ。
「人材が宝」と繰り返すも苦しい内田社長の心中
内田社長はFCCの黒字化時期について、「2021年度下期」としており、最低でもあと1年半は資金流出が止まらない。新型コロナの蔓延が長期化すれば、さらにFCCの黒字化は遠のく。
では、どうやって営業キャッシュフローを黒字にしていくのか。
決算発表と同時に打ち出した「事業構造改革計画」に盛り込まれたのは「スリム化」だった。現状720万台の生産体制を通常シフトで540万台にまで20%削減するという。そのために、インドネシア工場の閉鎖を正式に決めたほか、スペインのバルセロナ工場の閉鎖方針も明らかにした。インドネシア工場の閉鎖後はタイ工場に集約する。また、バルセロナ工場を閉鎖する一方で、EU(欧州連合)から離脱した英国のサンダーランド工場については維持する方針を明らかにした。
車種も2023年までに69から55に20%削減、新型車の投入を増やし、商品ライフサイクルを短縮、車齢を4年以下にするという。
もちろん、工場を閉めたからと言って、すぐに固定費が減るわけではない。「固定費を3000億円減らす」としているものの、具体策は出ていない。通常こうした構造改革には人員削減が不可欠だが、内田社長は「リストラではない」として、全世界で13万8993人(2019年3月末)いる人員数の削減計画については口をつぐんだ。欧米企業で事業規模を縮小する公表をしながら、人員計画を明らかにしないケースは極めて異例だ。
バルセロナ工場では早速、閉鎖反対を訴えて従業員がタイヤに火をつけ煙を上げるなどデモ行動が発生した。バルセロナの閉鎖には今後、政府や組合との交渉が必要で、退職手当など人員整理のための巨額の費用がかかる見通しだ。全体で2割生産量を減らせば、世界で2万人以上の解雇が必要になる可能性もある。
そうした「厳しい現実」を示せずにいるのだ。
内田社長は「優秀な人材が日産の宝だ」と繰り返した。その一方でリストラで人員を切るとは言えなかったのだろう。内部がなかなか一枚岩にならない中で、求心力を得ていないという不安があるのかもしれない。
社長候補とみられながら副COO(最高執行責任者)にとどまったことで日産を辞め、日本電産に転身した関潤氏は4月1日に同社の社長に就任した。それに続いて、6月1日には日産の上級幹部だった3人が、日本電産の執行役員に就任したことが明らかになった。縮小均衡を目指した途端、日産の求心力が失われ、ボロボロと人が辞めていっているわけだ。
社員の反発を恐れた「内向き思考」
かつてカルロス・ゴーン改革の時には、「ゲンバ(現場)は強い」と言い続けたが、一方で役員一歩手前の部長など日産的な中間管理職はスタスタと切っていった。今、縮小均衡を目指す中で、内田社長が考える「優秀な人材」とは誰を指すのか、幹部社員の多くが見えていない、ということだろう。
世界最大の自動車グループを目指したルノーや三菱自動車とのアライアンスの行方も不透明だ。決算に先立って、それぞれの企業が強みを持つ地域での役割分担を示したが、そうした「緩い連合」でこの先、生き残っていけるのか。
一時期は日産の経営権の完全掌握に動いたルノーも、新型コロナウイルスの蔓延に伴う欧州での販売激減などで、業績悪化が深刻だ。三菱自動車も苦しいままだ。そんな「弱者連合」で世界の市場で生き残っていけるのか。
内田社長はまた、「失敗を認める」「内向き文化を改める」と、これまでの拡大路線に走った日産との決別を口にした。だが、今期の赤字額を6712億円にとどめ、ゴーン改革時の6843億円を超えなかったのは、「史上最悪の赤字」と言われたくなかった「意思」の表れではないのか。リストラが不可欠なのにあたかも人員削減をしないで「規模適正化」ができるような説明に終始したのは、社員たちの反発を恐れた「内向き思考」だったのではないか。
現場の結束が果たせなければ、良い車は生まれないし、販売も伸びない。国内の日産ファンからも「欲しい車がない」といわれて久しい。縮小均衡を目指しながら、どうやって求心力を高めていくか。果たして、この危機を乗り越えられるか。内田社長のリーダーシップが問われている。
![Wedge (ウェッジ) 2020年 6月号 [雑誌] Wedge (ウェッジ) 2020年 6月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ibDjwyQwL._SL160_.jpg)